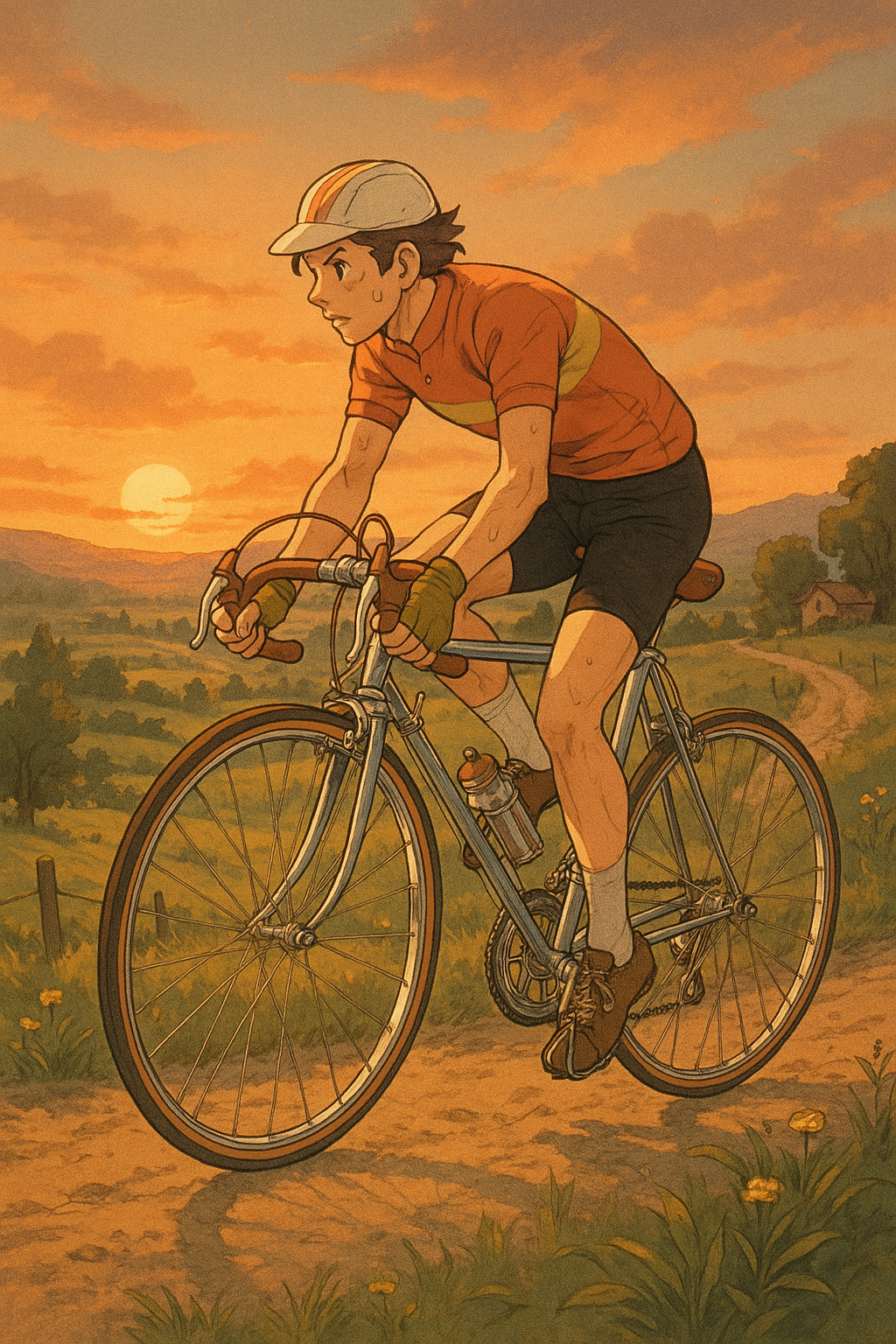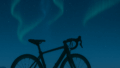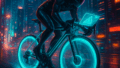はじめに
2125年、都市の道路はAI制御の自動車であふれ、空には輸送ドローンが舞う。
最新のテクノロジー型ロードバイクやロボットサイクリングが主役となり、速度と効率を競い合う時代だ。
しかしそんな未来の真ん中で、あえて「2025年とほぼ同じ設計」のロードバイクに跨り、汗と油の匂いを楽しむ人々がいる。
彼らが追い求めるのは便利さでも速度でもない。むしろ、不便さにこそ価値を見出す“レトロサイクル文化”である。
第一章:失われなかった感触
レトロ型ロードバイクの特徴は、何よりもシンプルさだ。
クロモリフレームに革サドル、スポークホイール、ワイヤーブレーキ。
変速は電子制御ではなく、ダウンチューブに取り付けられたレバーをカチリと操作する。
最新の自転車と比べれば、重く、効率も悪い。だが、ライダーはこう語る。
「ギアを変えるときの感触、坂を登りきったときの脚の疲労──それが心を震わせるんです。」
機械が走りを管理する時代に、自分の身体と機械だけで走る「純粋さ」が、人々を惹きつけてやまない。
第二章:週末のクラシックイベント
都市の片隅には、毎週末レトロサイクリストが集う広場がある。
そこでは古いフレームがずらりと並び、昭和や平成の歌謡曲がスピーカーから流れている。
年配のベテランは、磨き込まれたクロモリバイクを誇らしげに披露する。
若者たちはSNSで仕入れた情報を頼りに、古いパーツを必死に探し当てて持ち寄る。
「整備会」と呼ばれる光景では、工具と油にまみれた手で仲間同士が助け合う。
パンク修理をしながら笑い、時には余ったパーツを譲り合う。
そこにあるのは効率を追求する社会とは真逆の、“時間をかけること自体を楽しむ文化” だ。
第三章:若者たちの逆流
意外にも、レトロサイクル文化を支えているのは若い世代だ。
彼らにとって、最新技術は「生まれたときから当たり前」だった。
19歳の大学生・リナはこう語る。
「テクノロジー型は確かに便利。でも、それだと“自分が走ってる”感覚が薄いんです。
レトロは不便だけど、そのぶん全部が自分の身体に返ってくる。逆に新鮮で、映えるんです。」
彼女のSNSには、ヴィンテージジャージに身を包み、古いバイクで坂を登る姿が投稿される。
そしてその写真は数万件の「いいね」を集める。
レトロは単なる懐古趣味ではなく、デジタル世代にとって「未知の体験」として新しい価値を持ち始めている。
第四章:経済と観光を動かす
この文化はやがて都市経済や観光産業にも波及していく。
地方都市では「クラシックロードショー」が観光イベントとして定着。
旧車を展示し、昭和の音楽を流す会場には、若者も外国人観光客も集まるようになった。
さらに、職人たちが眠らせていた古いパーツ工房を復活させ、オーダーメイドの革サドルやクロモリフレームを作り直す。
その動きは、かつて忘れられた技術を現代に蘇らせることにもつながった。
こうして「不便さの美学」は文化を超え、地域の活力や新たな産業としての側面を持ち始めている。
第五章:未来へのメッセージ
レトロサイクル文化は単なる「懐古」ではない。
効率とテクノロジーに支配された社会の中で、人間が「自分で選ぶ生き方」を取り戻す行為である。
最新のAI自転車が事故を防ぎ、ロボットが災害を救う未来。
それでも、人々は「手間をかけて走ること」に価値を見出す。
その光景は、過去と未来をつなぎ、人間が何を大切にしてきたかを映し出している。
レトロ型ロードバイクは、単なる古い自転車ではなく、人間性そのものを映す文化遺産なのだ。
おわりに
2125年、ロードバイクは三つの進化を遂げた。
効率を極めるテクノロジー型、共生を体現するロボット型、そして“不便さ”を愛するレトロ型。
その中で、レトロサイクル文化は静かに、しかし確かに存在感を放ち続けている。
それは「過去を守る文化」ではなく、「未来に必要とされる人間らしさ」を体現する生き方だからだ。
次の記事👉 テクノロジー型ロードバイク ――都市を支配する「光の機体」
※本記事は2125年のロードバイク文化を描いたフィクションです。
ただし、現在進行中の技術革新やサイクリング文化の潮流をベースに構想しており、
「もしかしたら実現するかもしれない未来像」としてお楽しみいただければ幸いです。